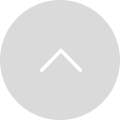過活動膀胱症状はQOLに影響が大きいものの、その原因は様々、ストレスも引き金に?
「尿に関する悩みを、国内の成人全体の8割近くが抱えている。」
そのような驚くべき結果が出たのは、2023年に日本排尿機能学会が22年ぶりに行った「下部尿路症状に関する疫学調査」です。1)
その中でも「急に起こる強い尿意」でトイレの悩みがつきないのが、「過活動膀胱」症状です。
突然、我慢できないほどの強い尿意をもよおしたり、そうした尿意切迫感のために何度もトイレに行かなければならないため頻尿になる、外出先などでトイレまで間に合わずにもらしてしまった、など、当事者の方には生活の質(QOL)に大きな影響がある疾患で、上記疫学調査の推計では、成人の約1,300万人、つまり10人に1人以上の方が罹患しているとされています。1)
- 1)20歳以上の約1,300万人が過活動膀胱に罹患していることが判明!尿に関する様々な症状の有病率や生活の質(QOL)への影響を調査 | 一般社団法人日本排尿機能学会
- Mitsui T, et al : Prevalence and impact on daily life of lower urinary tract symptoms in Japan : Results of the 2023 japan community health survey (JaCS 2023). Int J Urol 2024 ; Advance online publication.
doi: 10.1111/iju.15454. Epub 2024 Mar 21.
「過活動膀胱」の症状は、「尿意切迫感(がまんできない尿意)」とそうした強い尿意切迫感を伴う「昼間頻尿」「夜間頻尿」「切迫性尿失禁」の4つからなり、年齢が上がるにつれて症状が起こる方は増えますが、高齢者だけでなく、20代や30代の若い方でも症状が起こることがあります。
頻尿、尿もれや、突然起こる強い尿意(尿意切迫感)の症状は、多くの方が経験しており、日常の生活に支障を生じることも。しかし、「尿の悩み」で泌尿器科などの医療機関を受診する人はごくわずか。尿トラブルは、「人に知られたくない」、「加齢のせいでは」と我慢してしまう方が多いからのようです。
では、過活動膀胱の症状が起こる原因は何なのでしょう。
原因は主に2つ、脳や脊髄など神経の障害で起こる「神経因性」と、それ以外の要因で起こる「非神経因性」があります。過活動膀胱の大半は、非神経因性によると言われています。
非神経因性では、男性では前立腺肥大症の悪化、女性では骨盤底のぜい弱化の影響が大きいといわれています。これは、排尿に関わる身体構造が男性と女性では異なるためです。
上記に加えて、生活習慣の乱れ、加齢による自律神経のバランスの崩れや飲食物の影響などによっても起こることがあります。
次の項で、考えられるそれぞれの要因について、①ストレス、②加齢、③女性によくある要因、④男性によくある要因、⑤神経の障害(神経因性過活動膀胱)について、詳しく解説します。
①ストレス
非神経因性による過活動膀胱症状が起こる要因の一つに、「ストレス」もあります。心身にストレスがかかると自律神経のバランスが崩れ、それが引き金となって過活動膀胱症状が起こります。
緊張や心配事がたくさんあって、精神的ストレスがかかっている場合はもちろんですが、急激な気温変化、冷えや、ハードワークによる過労など、身体的なストレスも、自律神経が乱れやすくなります。また、アルコールやカフェインなど利尿作用のある飲み物が原因のこともあります。
過度なストレスを避けるためには、なるべく心身にかかるストレス負荷を減らすような日常生活を心がけましょう。また、精神的なストレス発散には、運動や趣味などで気分転換をはかったり、アロマテラピーでリラックスしたりするという方法もあります。
食生活や飲み物、ストレス対策など、日常での対策をしても改善しない場合には、お薬を服用する薬物療法も有効です。近年では様々な作用機序のお薬があり、専門医の診断を受けることで自分の症状を知るきっかけにもなります。また、セルフメディケーションとして、ドラッグストアや調剤薬局ではOTC医薬品も販売されています。専門医を受診する時間がない、もしくは病院を受診するのには抵抗があると感じる方は、一度薬剤師へ相談してみてもいいでしょう。
②加齢
加齢によって、全身(特に脳や骨盤内)の血管がダメージを受けていたり、自律神経のバランスが崩れたりすることで、正常な膀胱や尿道の機能が異常をきたし過活動膀胱症状が起こることがあります。
こうした「加齢による排尿機能への影響」は、生活習慣の改善や、膀胱訓練、骨盤底筋体操などが効果的とされています。また、すでに症状が生活に支障をきたしている場合は、お薬を服用する薬物療法もあります。
③女性によくある要因
過活動膀胱において女性特有の原因は、膀胱・子宮・尿道などを支える骨盤底筋が、出産や加齢の影響でダメージを受けてしまうことです。出産を経験している女性は、出産の際に骨盤底筋が大きく傷つくため、産後時間が経っても影響が残ります。
また、閉経に伴う女性ホルモンの低下により、膀胱や外陰部が過敏になったり、骨盤底の皮下組織のコラーゲンの低下などにより、骨盤底がぜい弱化している場合もあります。
これらの要因が重なって排尿のメカニズムがうまく働かなくなるのが、女性に見られる過活動膀胱症状の特徴です。
④男性によくある要因
男性の過活動膀胱症状は、前立腺肥大症の影響が大きくなります。
尿道を挟むように位置している前立腺が加齢によって肥大してしまうと、尿道が圧迫され尿が出にくくなります。初期のうちは、軽く肥大した前立腺が、膀胱の出口付近の三角部という場所の神経を刺激するため、頻尿や尿意切迫感を起こします。進行して前立腺が大きくなると、尿をなんとか出そうとして膀胱に力が入るため、膀胱に強い負担がかかり、正常な排尿ができなくなったり、さらに膀胱内に残尿が残るようになるので、排尿したばかりなのにまたトイレに行きたくなる頻尿や、尿意切迫感を生じるようになります。
⑤神経の障害(神経因性過活動膀胱)
「神経因性」過活動膀胱は、脳卒中などの脳の神経疾患や、脊髄損傷のような脊髄の神経疾患など、神経障害によって起こる場合があります。この場合、尿が充分に膀胱に溜まっていないのに膀胱が異常収縮してしまいます。特に脊椎疾患の場合は、尿道が開かないのに尿もれをしてしまい、高圧排尿になるため、腎臓が悪くなる可能性があります。
神経障害に由来する過活動膀胱の場合は、原因疾患の治療を優先すべきとされていますので、脳外科や整形外科など原因疾患の専門医を受診するようにしてください。
まとめ
急に起こる抑えきれない尿意や、頻尿、トイレに間に合わず失禁してしまうなど、生活の中で悩みがつきない「過活動膀胱」の症状。原因の大半は、ストレスや加齢による非神経因性とされています。生活環境を見直し、ストレス対策をしても症状が治まらない場合は、医療機関を受診して専門医の診断を受ける、薬局の薬剤師へ相談してOTC医薬品によるセルフメディケーションをしてみる、など、早めの対策が症状の改善につながります。
現在、過活動膀胱症状には様々な対策がありますので、ご自身に応じた対処を見つけることで、不安を解消できるとよいですね。気になる不調は早めに整えていきましょう。
【医学監修】関口由紀
女性医療クリニックLUNAグループ理事長。横浜市立大学泌尿器病態学客員教授。2005年横浜元町女性医療クリニック・LUNA開業。18年、ステージ別に「LUNA横浜元町」(2階)と「LUNAネクストステージ」(3階)に再構成。女性の生涯にわたるヘルスケアを実践。(www.luna-clinic.jp)
女性の一生涯にわたるライブスタイルを提案するインターネットサイト「フェムゾーンラボ」(www.femzonelab.com)の社長でもある。